IT活用で生き残れ現場発想システムが必要 第1回
第1回ポイント
- 顧客にとって、「欲しいものばかり売っている」品揃えを実現する理想のスーパーを目指すには、「客を知る」ことが不可欠。そのためにITは欠かせないツールである。
- IT活用は車の運転のようなもの。エンジンの仕組みを知るのではなく、ハンドルを切ると車がどう動くかを知ればよい。何ができるかを知ることが重要だ。
- 細分化する顧客のニーズを把握し、業務改善のためのシステムを作るには、もはや中央集権的な本部の力だけでは限界がある。今こそ、現場発想に基づく新しいシステムの提案が必要になる。
「行くと欲しいものばかり売っている」----。お客様にとっては、これが理想のスーパーです。裏返せば、ある特定の顧客層に対し、適切なマーチャンダイジングができている店ということになります。
スーパーのような特定多数の顧客を相手にする業態で、顧客の購買行動を正確につかむには、IT(情報技術)とそれを使いこなす力が不可欠です。本連載ではスーパーで動いている情報システムを、現場の人がどう活用していくかを考えます。第一回目の今回は、IT活用がなぜ必要かについて説明していきましょう。
「勘定系」と「情報系」に分類情報系ITの活用が重要に
スーパーの情報システムは、「勘定系」と「情報系」の二つに大きく分かれます(図1参照)。ここで言う「勘定系」は、POS(販売時点情報管理)システムや物流、受発注など、スーパーの基幹業務を支えるシステムです。
一方、「情報系」とはPOSデータを基にした売り上げ分析や、顧客管理と連動したCRM(注1)(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)、情報共有のためのナレッジマネジメント・システム(注2)など、様々な情報を駆使して、より良い品揃えや顧客サービスを目指すためのシステムです。
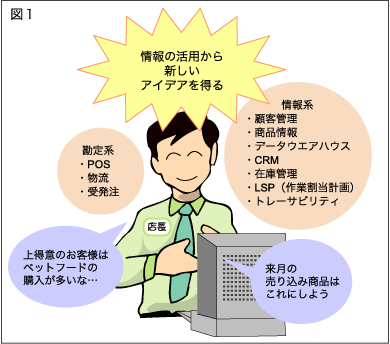
図1
スーパーの現場では、この「情報系」の活用がより重要になります。様々な情報から、売り上げ向上やコスト削減の方策を科学的に考える。口で言うのは簡単で、実行は難しい問題です。しかし、IT活用が生産性を高めるカギであることは間違いありません。
ITを使いこなせる店長は、自分の店の「ポジション」をつかむのが上手です。POSデータやP/L(損益計算書)などの定量的な情報と、現場の観察や経験などの定性的な情報を突き合わせ、仮に目標から離れてしまっても対策を正しく立てられるからです。
IT活用を難しく考えることはありません。ITも道具の一つであり、いわば自動車の運転と同じです。エンジンの仕組みを知らなくても、車両感覚や車の挙動が分かれば十分なように、IT活用でここまではできる、という利用者の感覚を持つことが大切です。
「現場発想」の情報システムが生産性向上のカギとなる
現場がITへの理解を深めることは、スーパーという業態全体にとっても重要です。それは、これからの小売業の情報システムは、「顧客起点」「現場発想」で作られる必要があるからです。
現場での経験から言うと、かつての「2割のお客様が8割の売り上げを支える」という「2:8」の法則は崩れつつあります。今は「3:7」くらいでしょう。顧客の好みが、どんどん多様化しているからです。
この顧客層の細分化は、今後ますます進むはずです。当然、地域対応や個店対応がより重要になり、それには業務プロセス全体の見直しと、ITによるシステム化が欠かせません。
ところが、上の図2のような今のスーパーで利用されている情報システムは、機能の多くが本部に集中する「中央集権型IT」です。
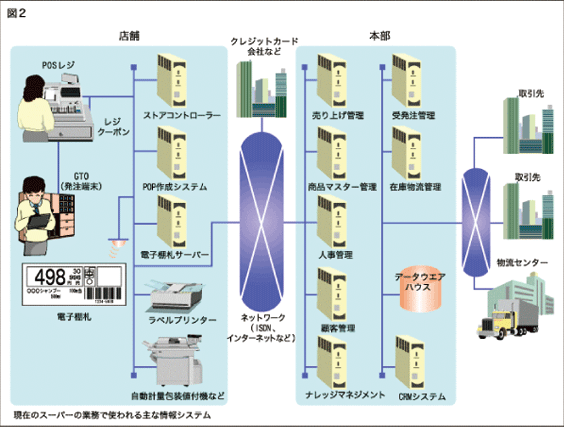
図2
これに対し、これからの時代に必要なのは、地域対応や個店対応に適し、現場である店鋪が売り上げ分析や販売計画を立てられるような「分散型IT」です。そして分散型ITは、本部の情報システム部だけではなく、顧客に最も近い現場から「我々が必要とするITはこうあるべきだ」と提案しなければ作れません。
本部の情報システム部門は、現行システムが停止しないように運用・保守する立場から、店や顧客にとって役立つと知ってはいても、現行システムに影響するような変更はしたくないのが本音です。これを納得させるには、新しいIT活用で売り上げがこれだけ伸びる、生産性が高まりコストがこれだけ下がる、というように、現場が情報システム部門とケンカできるくらいのITに関する知識が必要になります。
現場がITについて知識を深めることは、より効率的で儲かるチェーンストアを自分の力で作り上げるチャンスでもあるのです。
POS、物流、受発注"三種の神器"を見直す 第2回
特売の展開方法が複雑になるにつれ、POSシステムに大きな負荷がかかるようになる。販促部門や店舗が「本当に業務に必要な特売なのか」を考えることが、投資効果を高める上で不可欠になる。
物流面では産直品など店に直接配送される「店直」が増え、検収作業を繁雑にしている。現場から意見を出しながら伝票の標準化やオンライン化に取り組み、作業効率の改善を図る必要がある。
受発注システムは、伝票をやりとりするという視点だけではなく、いかに全体の発注精度の向上につながるか、という視点から構築することが望ましい。そのためには現場の作業手順や意見が必要になる。
今回は「POS」「物流」「受発注」というスーパーの根幹を支える三つのシステムについて、現場が積極的にシステム構築に参加していく必要性について解説します。普段は存在を意識せずに利用しているシステムですが、本来は現場の意見や視点から構築することが重要なものなのです。
本当に必要な特売なのかPOSへの負荷を見直す
現場から見れば、POSは動いて当たり前。なぜ現場がPOSに口を出す必要があるのか?と疑問に思われるかもしれません。その疑問に答えると、今のままだと、POSへの負荷がどんどん高まり、"破たん"をきたしかねないからです。
日本のスーパーでは、特売の処理がPOSの大きな負担になっています。月間お買い得品、会員限定商品などのほか、複数の特売条件が重なるときの優先順位など、特売のアルゴリズムはとても複雑です。そのため、POSの誤登録やPOPでの表示売価との食い違いといった、重要なミスの原因にもなります。
日本の一般的なスーパーでは、POSにかかる負荷は、特売処理と定番商品の処理で50対50にも達します。つまり、もし特売がなければ、POSの性能は半分で済むのです。スーパーの店舗システムにおいて、POSへの投資は半分以上を占めます。仮にチェーン全体のPOSレジを入れ替えれば、発注は1000台単位となり、10億円くらいかかります。
米ウォルマート・ストアーズ社など、EDLP(エブリディ・ロープライス)型の企業は、特売がないのでPOSの機能もシンプルで済みます。システム投資も低く抑えられ、ローコスト経営を図る上で見逃せない差となります。もちろん日本で特売をすべてなくすのはナンセンスですが、どの特売が本当に必要かという、現場視点・業務視点からの見直しは不可欠です。
また、本来はPOSの処理上、特売扱いにする必要がないのに、特売扱いで処理している商品も見受けられます。例えばギフトを特売扱いにしている場合が少なくありません。こうした場合は、例えば売価を下げて登録し、定番商品として扱うなど、現場とシステム部門が共同で、POSの負担を減らす工夫が必要です。
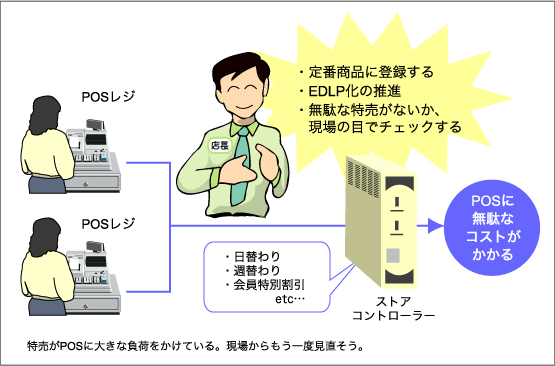
図3
「店直」を例外にしない物流システムにも口を出すべき
入荷や品出し作業は、店舗の全作業のおよそ50%を占めています。ここ数年で、CDC(CentralDistributionCenter)などによる物流の集約化や、伝票処理のオンライン化が進み、店舗での検収作業の軽減や通路別配送など、作業の省力化が進んできました。
しかし、一方で"逆行"する動きもあります。CDCなどを通さず、店舗に直接届く「店直」が増えているのです。店直には地場の産直野菜などの産直物や、冷凍食品などが含まれます。この店直は、伝票の形式がバラバラだったり、作業手順が統一されていない場合が多かったりするのが実情です。
現在、店直はあくまで通常の物流業務の中でのイレギュラーな処理という位置付けです。しかし、個店対応への取り組みが重視されている現在、店直は増えこそすれ、減ることはないでしょう。例外扱いをやめ、店直への対応を含めた物流の最適化を図り、商品の伝票処理の見直しや、オンライン化による伝票レスの仕組みなどを考える必要があります。
このときに現場から提案できることは多いはずです。店直を検収する際のチェック項目を減らす、見やすい伝票の形式を作るなど、店舗がどのようにしたいか、という意見を取り入れるだけで、作業量が格段に変わってきます。
プロジェクトチームで発注精度の向上に取り組む
HT(ハンディターミナル)やGOT(グラフィックオーダーターミナル)で、画面上の棚割りや在庫数を見ながら発注数を入力するなど、店舗での発注作業にもITが入り込んできました。受発注のオンライン化も進んでいます。
しかし、受発注システムを作る上で本当に大切なのは、どれだけ安全・確実に発注データをやりとりできるか、ではありません。発注精度を高めて、チャンスロスと廃棄ロスの二つのロスを最小限にすることが重要なのです。それには受発注だけでなく、販売予測や在庫管理など、様々なシステムとの連携が必要になります。
既存の縦割りの組織では、情報システム部門は安全なシステムの構築にかかりきりで、全体の視点を忘れがちです。プロジェクトチームを結成するなど、横断的な組織で取り組む必要があります。そこで最も大切なのが、現場がどうしたいか、という意見です。
特に日本のスーパーで発注精度の高い受発注システムを作ろうとすると、避けて通れないのが生鮮品の扱いです。例えば丸魚から切り分けて刺身パックを作って販売したり、生鮮部門の材料で惣菜を作った場合など、販売する商品と発注商品が違うため、正確な在庫把握が難しいからです。
カスミの経験では、生鮮品についても諦めずに頑張れば発注精度を上げるシステムができる、という結果になりました。営業部門がプロジェクトの主導権を握り、店舗の意見を徹底して吸い上げるなど、現場主義の取り組みが成功のカギとなったのです。
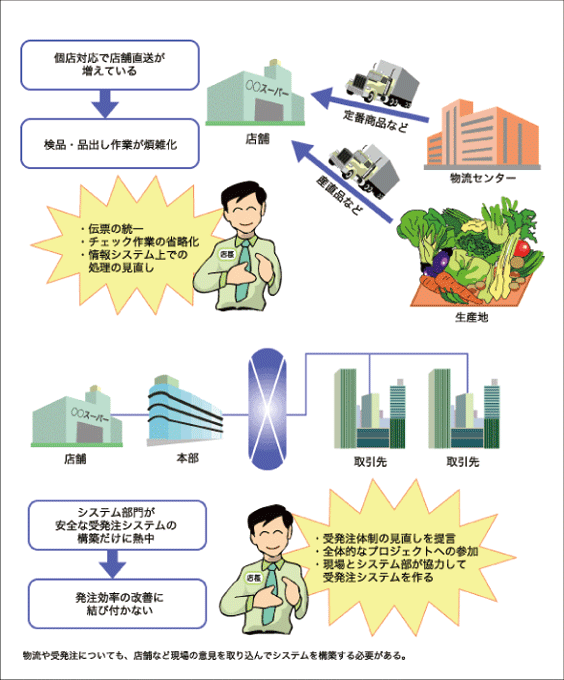
図4
「データウエアハウス」を現場の意志決定に活用 第3回
第3回ポイント
- データウエアハウスは「情報の倉庫」。裏付けのある意志決定をする上で役に立つ。米ウォルマート・ストアーズなどが率先して活用に取り組んできた。
- POSデータといった定量情報の蓄積だけでは不十分である。店舗における売り方や催事情報なども取り入れた「定性情報」の組み合わせが必要だ。
- データはためるだけでは意味がない。現場が簡単に使えるシステムを最初から考えるべきだ。日々の意志決定に役立ててこそ、データウエアハウスは意味を持つ。
「データウエアハウス」という言葉をご存じでしょうか?直訳すると「データの倉庫」です。様々な形で社内に分散している顧客の購買履歴や、販売データ、在庫などの必要な情報を一元的に集めるデータの倉庫を作り、経営や店舗運営における意志決定に利用できるようにしたものです。
データウエアハウスの活用で、先進的と言われているのが、米ウォルマート・ストアーズです。1990年代から開発を進め、200テラ(200兆)バイト以上という膨大なデータを扱えるシステムを作り上げました。
このシステムでは誰がいつ、何を買ったかという顧客の購買履歴や商品データ、在庫データなどを過去2年分蓄積しています。ウォルマートがデータウエアハウスを使った分析から、一見全く無関係に見える、「おむつを購入する消費者は同時にビールも購入する」という関係を発見したというエピソードはあまりにも有名で、もはや伝説になりつつあります。
しかし、データウエアハウスに対しては、誤解が多いのも事実です。最たるものは「POSデータを集めればデータウエアハウスになる」という、安直な考えでしょう。
「POSだけでは役にたたない数値化できないデータが重要
データウエアハウスは、単純なPOSデータの分析ツールというだけの位置付けのシステムではありません。本当のデータウエアハウスは、どうしたいか、という意志決定に役立つための情報が、ポンと出てこなくてはいけません。これは、POS中心主義ではできないことなのです。
POSで分かるのは、何がいつ、いくつ売れたかということだけです。それ以上のものではありません。POSデータは売れたものについては分かりますが、「なぜ売れたのか」あるいは「なぜ売れなかったのか」といった理由を判断するには、情報として不十分なのです。
これまで申し上げてきたように、私はこれからのスーパーは、個店化の流れが避けられない、と考えています。お店のある地域に合わせた品揃えや売り方を実現する上で、重要なのは「数値化できないデータ」なのです。例えば、商圏内の学校は、いつからいつまでが夏休みなのか、遠足は何月何日か、そのときの天気予報と実際はどう違ったのか--。こうした文章によるデータが重要です。
さらに商品の売り込みはエンドや平台など、店内のどこで販売したのか、そのときの天気はどうだったか、POPやノボリの設置など、どのような販促を試みたのか。「あの時はこういう形で売り込んだ」という記録がなければ、意志決定の基準になりにくいのです。
今まで、これらの情報を統合して判断するのは、店長など個人の能力に頼ってきました。確かに能力のある店長であれば、情報システムがなくてもできることです。
しかし、チェーンとして考えたときに、それでは問題があります。転勤によって店長が変わると、ノウハウも一緒に流出してしまうからです。情報システム化で、共有すべき情報は共有し、簡単に取り出せるようにする。こうした「ナレッジマネジメント」の視点が重要になっているのです。
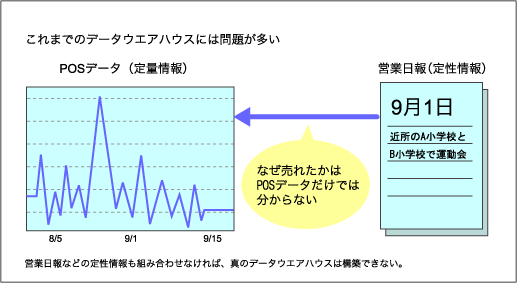
図5
定性情報の扱いにも可能性が現場主導のシステム構築を
実は定性情報というのは、コンピューターが苦手とする情報です。コンピューターは数値の計算は得意ですが、「意味」を理解することはできないからです。しかし、技術も進歩しており、最新のデータベース技術では、例えば「山へ行った小学校の遠足で売れた商品」などの文章で、データウエアハウスを検索して該当するデータを表示させる、といった定性情報を扱うための研究が進んでいます。
カスミでも実験として取り組んでみたことがあります。まだ技術的な課題はあるものの、「店舗の特性を考えると、この商品は全店の平均的な動きよりも3日早く動き出す」「発注数量が多めでも売り切れる」といった意志決定する際の裏付けとして役立てることができるようになり、これから有望な技術であると感じました。
重要なのは、データウエアハウスもまた、現場の社員が利用するために存在する、ということです。データを本部がため込んで満足しまうのではなく、現場が頻繁に利用するものであってこそ意味があります。
どうしても「店舗の情報を一元的に収集し、分析できるようにする」データウエアハウスの性格上、プロジェクトは本部主導で進んでしまいがちです。
しかし、データウエアハウスが何のためにあるかと言えば、それは現場の社員のためなのです。ウォルマートの情報システムも、取引先を含めて、現場の社員が自ら分析し、意志決定できるようにした分散型のシステムです。
現場からの視点は、あらゆる情報システムに不可欠なものになってきていきますが、現場経験のない情報システム部門と、取引先であるシステム構築業者だけでデータウエアハウスを作ると、費用ばかりかかって「現場が使えないシステム」になってしまうことが多いのです。
そうならないためには、データウエアハウスを構築する際に現場からの積極的な参画が必要になってきます。構築プロジェクトの音頭は、販売推進部長やスーパーバイザーなどが取ることを勧めます。
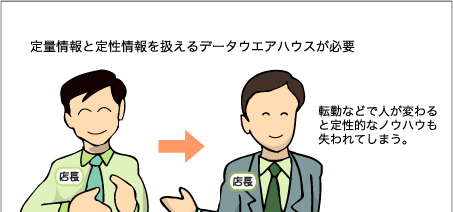
図6
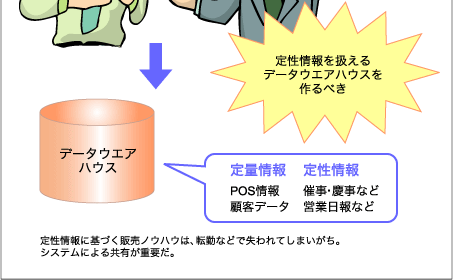
図7
ポイント乱発は効果薄CRMは品揃えに活用 第4回
第4回ポイント
- CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)は「お客様との関係をマネジメントすること」。いかに「ひいき客」になってもらい、店を長期間利用してもらうか。そのための経営手法である。
- ポイントカードやクーポンの発行だけでは、単なる値引きにとどまってしまい、本当のCRMにはつながらない。
- CRMはお客様の情報をいかに集め、個店が分析できる仕組みを作るかが、成否のカギを握る。顧客の購買データやお客様相談室に寄せられた声の蓄積の中から、消費者が満足する品揃えを実現するマーチャンダイジングの仕組みを作ることが重要。
今回は小売業にとってのCRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)についてお話しましょう。CRMを日本語に訳すと「お客様との関係をマネジメントすること」です。
CRMは、目先の収益だけを追い求めるのではなく、一人ひとりの顧客との取引関係の維持を重視します。顧客が企業にもたらす、生涯にわたる価値(LTV:ライフタイム・バリュー)の最大化を目的としているのです。
このように書くと難しく感じるかもしれませんが、要は「ひいき客、常連客との末長いお付き合い」をいかに実践するかを重視した経営手法なのです。昔はCRMという言葉を使うまでもなく、こうした商売は当たり前にできていたことです。鮮魚店や青果店、いわゆるパパママストアでは、顧客一人ひとりと顔見知りで、昨日何を食べたか、今日は何を薦めるか、といったことが自然に行われていました。それをチェーン化による集中購買・量販化の中で切り捨ててきたのです。
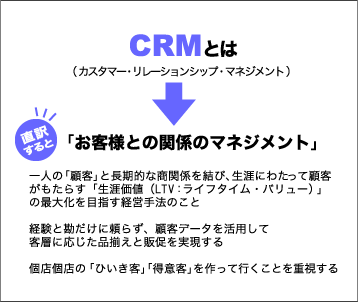
図7
安易なCRM導入は効果薄値引き合戦になりやすい
CRMは日本でも90年代後半から流行を巻き起こしました。しかし、CRMには多くの誤解がつきまとっています。その一つが、「ポイントカードやクーポンを導入しさえすれば、CRMを実践できる」という考え方です。
ポイントカードやクーポンで、優良客を優遇するという考え方は、一見、理がありそうです。小売業は2割の優良顧客で8割の売り上げを稼ぐ「2:8」が理想とよく言われます。その2割の顧客を優遇するのは、納得できる話に思えます。 しかし、実際にはポイントカードなどを発行しただけで、単なる値引き合戦のツールになってしまっているケースが多いようです。利益を圧迫してしまった結果、最近ではやめてしまうところも出てきました。様々な調査で裏付けられていることですが、一般的にスーパーへの来店動機として最も多いのは「(家に)近いから」です。次いで「品揃え」が来るのが普通です。ポイントの付与による実質的な値引きは、顧客の来店動機の直接の決め手にはならないのです。
小売業のCRMはMDのためPOSに頼ると失敗する
それでは、小売業にとってCRMの本筋とは何でしょうか。CRMの目的は、顧客が店に愛着を持ってくれること、つまりストアロイヤリティを高めることです。しかし、ストアロイヤリティは価格面でのインセンティブに頼るのではなく、あくまでマーチャンダイジングや店員の顧客サービスで獲得するものだ、ということです。この連載で繰り返してきたことですが、欲しい商品がいつもあるスーパーが、顧客にとって最良のスーパーなのです。
しかし、スーパーは特定多数の消費者を相手にしています。多数の消費者の期待にこたえる品揃えを、限られた売り場で常に実現し続けることは、並大抵の努力ではできません。それでも、今のスーパーに求められているのは、正にそのことなのです。
記憶しきれないほど多数の来店者が満足する品揃えを実現するには、お客様のデータを可能な限り集め、分析できるITの助けが必要です。しかし、単純にPOSデータに基づくPI(PurchaseIndex:1000人当たりの購買点数)値だけを頼りに、マーチャンダイジングを進めるのは危険なことです。全体ではあまり売れていないけれど、優良顧客が来店時に必ず買う商品があったりするからです。単に売れていないからといって、その商品を切ってしまうと、優良顧客そのものを失う可能性があるのです。
こうした難しい問題に対処するには、顧客一人ひとりの購買データと、サービスカウンターに寄せられるクレームや要望を一括して管理する仕組みが必要です。この仕組みを作ることが、食品スーパーにとって本当のCRMです。
食品スーパーにおけるCRMの実践には、商圏の状況が大きく影響してきます。これが絶対的な正解、というものはありえません。例えば東京都は、区によって毎年1/4の居住者が入れ替わります。こうした地域では、顧客との長期的な関係がそもそも維持しにくく、顧客データを集めても短期間で古びてしまいます。また都市圏では、自分の名前を企業に知られることを快く思わない顧客層が多く存在します。
「アクション」を先に決め顧客情報の収集を始めるべき
大切なのはCRMによって何がしたいのか、つまり目的のアクションを先に決めることです。それによって、どんな顧客情報を集めるかが全く異なってきます。例えば、お客様の名前をお呼びしてあいさつをしたり、誕生日にプレゼントを渡す、といったアクションを起こしたいとします。こうした場合には名前や誕生日などの情報を取得する必要が出てきます。しかし、こうした計画がなければ、誕生日の取得は不要な項目です。
また、これもCRMにまつわる誤解ですが、CRMを実践する際にチェーン全店が足並みをそろえる必要はありません。地域ごと、店ごとに内容が変わってもいいですし、顧客データの集め方が店ごとに異なってもいいのです。むしろ地域性を無視するような画一性を求めると、本来のCRMの理念とかけ離れていきます。CRMはあくまで、個店の力を上げるためのツールです。個店ごとのカスタマイズと活用が可能な、柔軟なCRMの仕組みが今後は重要になってくるでしょう。
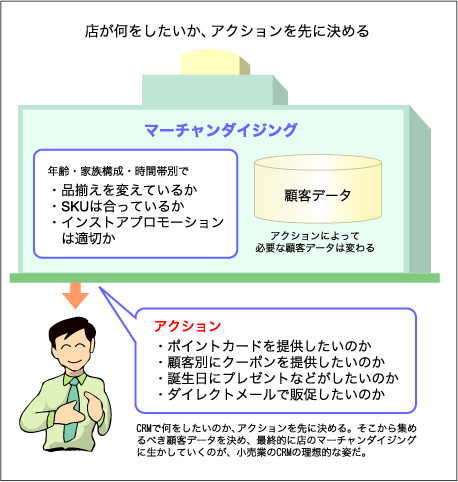
図9
"前年実績"は役立たない個店主導の販売予測を 第5回
第5回ポイント
- 今年のような冷夏では、前年実績に基づく販売予測の精度は著しく低くなる。しかし勘頼みや本部の指示待ちでは、ますます売り場は乱れて売れなくなってしまう。
- 本部による中央集権的な仕組みで、個店ごとに正確な販売予測を立てるのは無理がある。販売予測の精度を高めるために、個店ごとに細かくデータを見ていける仕組みが必要になる。
- 販売予測は現場が立て、本部はその意志決定に役立つツールをITで提供すべき。これは情報システムだけではなく、会社全体の仕事の進め方に関わる問題で、本部が現場を信用していなければ不可能だ。
明日、今週、今月、何をどのように売るか?売り場をどのように作れば予算を達成できるか?こうした販売予測は食品スーパーで働く人々にとって、日々、当たり前にやっている基本的な作業です。販売予測は、売価、天候、地域性、フェース数、POPの有無、チラシ、関連販売の有無など、様々なデータを考慮して計算する必要があります。しかし、今年の夏は10年ぶりという近年まれに見る冷夏でした。事前の販売予測が外れてしまい、売り上げの低迷やロスの増加に悩まされた食品スーパーが少なくないのではないでしょうか。
根拠が乏しい前年実績勘や本部の指示待ちも危険
販売予測でありがちなのは、「昨年はどうだったか」と、すぐに前年の実績を持ち出すことです。ここには大きな落とし穴があります。特に今年のように冷夏では「前年比」というデータはあまり役に立ちません。特に気温で売れ行きが左右されやすいドリンク・日配品などの商品については、全く役に立たないと言っていいでしょう。
さらに言えば、来年の夏の販売予測を立てるために、冷夏である今年のデータを活用しても、根拠が乏しいデータにしかなりません。猛暑だったり冷夏だったり、気温の変動が激しい昨今では、販売予測を前年実績だけに頼ることは難しくなっているのです。
それではどうすれば良いのでしょうか?多いのが、個人の勘や本部の指示待ちに走ってしまうことです。こうすると問題はより深刻になり、さらにモノは売れなくなります。
一般的に言って、暑い夏よりも寒い夏は、確かにモノが売れません。飲料やビールは気温の影響を大きく受けますし、雨が降り続ければ来店客数は減るのが普通です。
しかし、売れないのは、それだけが原因でしょうか?個別の商品の特性や販売見通し、個店ごとのお客様の購買動向などを、正確に把握した結果の不振だったのでしょうか?
これは、環境の変化に対応できない、今の販売予測の仕組みそのものに問題があります。今やITは販売予測に欠かせないツールですが、多くの販売予測システムは前年のPOSデータに頼っているのが実情です。この仕組みを考え直さない限り、"前年実績の呪縛(じゅばく)"は付きまといます。非常に難しい問題ですが、この問題の解決に挑戦していかなければなりません。
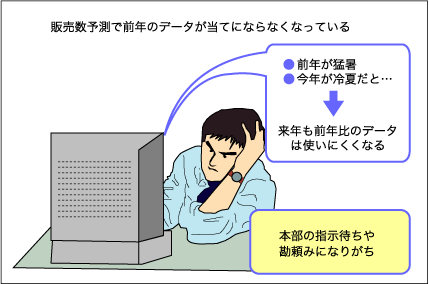
図10
ITの進歩に伴い個店情報の管理が可能に
個店の情報をどう生かしていくかが、販売予測でもカギになります。優秀な店長の中には自分で表計算ソフトなどのマクロ計算プログラムを利用して、自分の店で売れた商品や売れなかった商品、そして、そのときの売価や天候、展開した販促方法といった情報を管理し、販売予測に役立てています。
こういった現場の知恵を、本部は吸収して生かしているでしょうか?本来のチェーンストアの原理原則からいうと、本部レベルで個店の情報をすべて管理するのは、かなり難しいと言えるでしょう。本部の役割は個店の差異をできるだけ取捨選択して、全体を見るのが仕事だからです。確かに個店のコントロールを本部が行っているチェーンもあります。しかし、これが行き過ぎると、本部の間接費がかかりすぎてコスト高になるでしょう。
個店に関する情報を、コストをかけずにどう管理していくかは、これからの食品スーパーにおけるITの大きな課題です。しかしパソコンの高機能化やインターネットの普及により、大規模なホストコンピューターを本部に置く中央集権的なシステムを作らなくても、各店ごとに分散させる仕組みを作ることが可能になっています。
ITは「分散指向」に動いており、個店対応に向かうチェーンストアの変化にマッチしているのです。
本部が提供する役割は「使える武器を低コスト」で
では、現状の情報システム部で対応できているかというと、そうでない場合がほとんどです。しかし、これは情報システム部門だけに責任があるわけではなく、会社全体のあり方の問題です。個店主導の仕組みは、本部と店舗の役割を再設計し、ITの使い方や現場の行動、社員に対する教育と、すべてがかかわる問題になります。
そもそも個店主導の仕組みを作る上では、本部がチェーン全体の販売を予測するのではなく、各店がそれぞれ販売予測を立て、その合計がチェーン全体の販売予測となる、という体制でなければなりません。しかし、本部は「店舗に任せては信用ならない」とコントロールしたいのが本音でしょう。それで良い時代があったのも確かです。
しかし、状況は変わってきています。就職難の昨今では、優秀な社員や高い能力を持ったパートを採用しやすくなっています。現場の"考える力"のポテンシャルは高まっているはずなのです。そこで本部に求められるのは、こうした人たちにITで情報武装してもらう仕組みを、いかに低コストで作り上げるか、ということです。
戦争に例えれば、現在は戦況が不透明で、いちいち大本営にお伺いを立てていては十分に戦えません。そこで各部隊が個別判断で戦うのがベストになってきます。このときに意志決定に役立つ"武器"があれば現場も心強い。こうした"武器"を提供し、店舗をサポートすることこそが、これからの本部の役割として重要なのです。
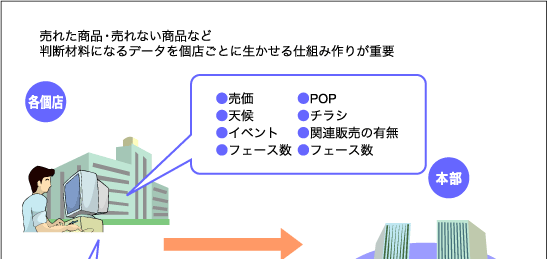
図11
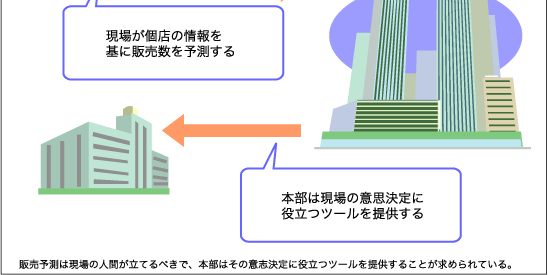
図12
在庫は単品で管理する生鮮でも手順次第で可能 第6回
第6回ポイント
- 多様な商品を扱う食品スーパーにとって、在庫管理は非常に難しい問題だ。商品のロケーション管理をはじめ、生鮮とドライの管理方法の違いや、在庫計算のあいまいさといった問題点がある。
- 食品スーパーの在庫管理は、ITを活用した単品管理システムを導入することが理想である。一品ごとの原価・粗利益・在庫数を把握できてこそ、適切な利益管理が可能になる。
- 現在、様々な食品分野で課題となっているトレーサビリティも、突き詰めれば単品管理と切り離しては考えられない。単品管理の仕組みを作ることが、消費者にとってもメリットをもたらす。
食品スーパーにとって、在庫管理は適切な利益を確保する上で欠かせません。過剰在庫は収益を圧迫し、在庫が不足しても販売チャンスを逃します。しかし、食品スーパーのように1万アイテムを超える商品を取り扱う業態では、各店ごとの正確な在庫数を常時把握するのは非常に難しいのが実態です。
在庫管理の理想は単品管理三つの課題の解決が必要
私は、これからのスーパーの在庫管理はIT(情報技術)による単品管理が重要だと考えています。商品1個1個について、いくらで仕入れて、いくらで売ったかが明確に分かるようにし、在庫は原価で100円の商品が12個、120円のものが10個というように、単品ごとに在庫数と粗利益、原価を厳密に管理することが理想です。
現在の食品スーパーで、店頭の在庫を正確に把握しようとすると、棚卸しをして実際の商品の数量を数えるしかありません。しかし1万アイテムを超える商品を取り扱うスーパーでは、人員とコストがかかる棚卸しを頻繁に行うことはできません。多くは計算により在庫高を求めていますが、これは後述するように実際の在庫と誤差が発生しています。
食品スーパーにおける在庫管理の難しさは、大きく分けると次の三つがあると考えています。
- ロケーション管理の難しさ
- 生鮮部門の在庫管理の難しさ
- 在庫の計算方法の不正確さ
順に説明していきましょう。まず(1)のロケーション管理の問題です。スーパーでは商品がバックヤードにどれだけあり、売り場にどれだけあるか、正確に把握するのは困難です。特に夏場のドリンク類など、売り場への補充が頻繁になるものについてはなおさらでしょう。
次に(2)の生鮮での在庫管理の難しさがあります。現在は生鮮食品のインストア加工が盛んです。これらの生鮮食品は、入荷した材料を店内で加工して商品化します。例えばロース肉のブロックから、焼き肉用やしゃぶしゃぶ用など様々な商品を作ります。入庫形態と販売形態が変わるために、在庫管理は非常に難しくなってしまいます。
在庫管理の解決すべき問題
- 売り場にあるのか、バックルームにあるのか、在庫のロケーション管理があいまい。
- 生鮮とドライで管理方法が異なる。特に生鮮は原材料として入荷し、商品化して販売するので、正確な在庫管理をしようとすると難しい。
- 在庫高の計算をケース売価などによる「ひと山いくら」といった"どんぶり勘定"で行っており、正確性に欠ける。
ITによる単品管理で様々なロスの低減を図る
最後の(3)の問題です。在庫高を帳簿から計算で求める方法は、食品スーパーの多くで使われています。この場合の在庫高の計算は、単品の原価を積み上げると計算が煩雑になるため、カテゴリーごとに、売価に原価率をかけたものの合計を求めます。似た原価率の商品をまとめてカテゴリーとして扱うことで計算は簡単になるのですが、ある意味「どんぶり勘定」であるため、計算上の数値と実際の数値では誤差が生じてきます。「不明ロス」として処理されるものですが、これが5.10%にも及ぶ場合があるのです。
食品スーパーの経営は、廃棄ロスや値引きロスといったロスとの戦いです。しかし在庫のそもそもの計算方法が厳密性に欠けると、正確なロスも分かりません。つまり根本的な解決には、従来の計算方法から抜け出す必要があるということです。そこで、IT活用による単品管理が必要となるのです。
もとより、単品管理は製造業では当たり前です。部品単品ごとの利益を厳密に管理するといったことは、製造業に一日の長があります。こうした製造業の長所は流通業でも取り入れるべきでしょう。 現在ではテラバイト級のデータを管理するような大容量・高度なシステムを、以前よりも低コストで構築できるようになっています。商品単価が安い流通業でも、単品管理が可能な状況は整ってきているのです。
単品管理による在庫管理ができ、粗利益や原価の計算が単品単位でできるようになってはじめて、商品のSKU(在庫管理単位)の数や、1パック当たりに商品がいくつ入っているか、という入り数の問題、適切な値入率といった問題について、データを見ながら判断できるようになるのです。
単品管理ができればトレーサビリティも可能に
食品業界では、いまだに一つひとつの商品を追跡する仕組みができていません。食品は日持ちしないので、3.4日しか保たない在庫をわざわざ単品ごとにデータ管理する必要はない、と考えられているのです。
しかし、この考え方が時代遅れであることは明白です。これからの社会では、消費財がただ消費されるだけではなく、どこで生産され、加工されたのか、といった情報まで含めて伝達されることが求められています。一つひとつの商品に対するケアが重要になっている中で、企業として対応ができていないのが問題です。
実は単品管理とトレーサビリティは、表と裏の関係です。トレーサビリティとは、商品単品の生産から販売までの履歴を追跡すること。単品を管理する、という点については、単品管理とトレーサビリティは変わるところがありません。ITにおける情報の扱い方は、ほぼ同じなのです。
粗い業務では単品管理は無理業務手順の見直しも必要に
これまで単品管理システムの構築に取り組んだ経験から言うと、生鮮品も含めて、単品管理はやろうと思えばできます。しかし、大きな問題が一つあります。ロケーション管理は適切か、商品がマニュアル通りに正しく作られているかといった、店の業務の精度に依存する部分が大きいということです。
経験上は、鮮魚や惣菜部門は比較的レベルが高い単品管理が可能でした。これは既に実際の業務が、細かく定められているからでした。一方、青果部門では単品管理は思うように進みませんでした。商品マスターへの登録をはじめ、商品化の手順などについて、業務に粗い点が見られたからです。単品管理を適切に行うには、まず現場の業務手順を細かく設計する必要があるということです。
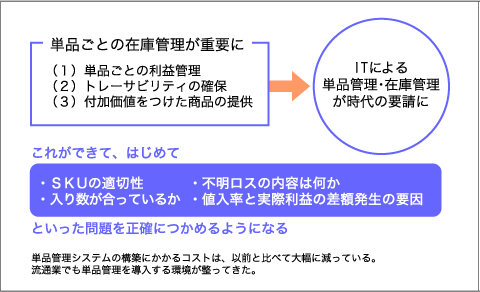
図13
- 注1:カスタマー・リレーションシップ・マネジメントの略。顧客一人ひとりと長期的な取引関係を築き、各顧客が生涯にわたってもたらす利益(生涯価値)の最大化を目指す経営手法。
- 注2:成功ノウハウや知恵を共有することで、企業全体の競争力を高める経営手法。「知識管理」「知識経営」と訳される。

